- 借地権HOME
- 借地権の評価について
【この記事のまとめ】
- 借地権は種類によって評価方法が異なります。
普通、定期、一時使用目的など種類があり、それぞれ評価方法が異なるため確認が必要です。 - 相続税評価額は種類で計算方法が異なります。
普通借地権は自用地価額に借地権割合を乗じ算出。定期借地権は残存期間なども考慮されるなど、種類によって計算方法が異なります。 - 借地権相続は注意点が多く専門家相談が重要です。
借地権相続は、契約内容や地主の承諾、地代変更など注意点が多いです。正確な評価とトラブル回避のため、専門家への相談を推奨いたします。

監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
借地権とは
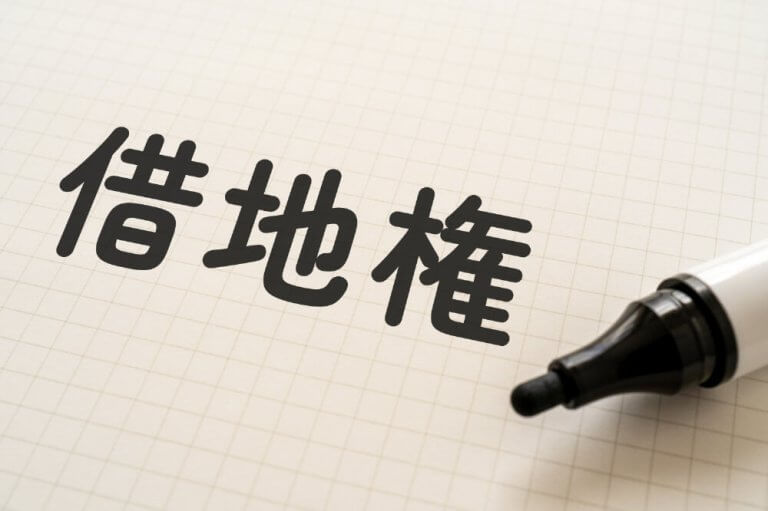
- 普通借地権
- 定期借地権
- 一時使用目的の借地権
普通借地権
普通借地権は住宅などの建物を建てる目的で設定される借地権です。法律で定められた契約期間は30年以上で、期間終了後も更新する権利が認められています。
定期借地権
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
一定定期借地権の契約期間は50年以上で、更新や建物買取請求権はありません。契約が終了すると土地が必ず返還されるため、所有者にとっては安定的な利用が可能です。
事業用定期借地権は事業用目的で土地を借りる場合に設定され、契約期間は10年以上50年未満です。商業施設や工場などの事業用の土地利用に適しており、契約終了時に土地が返還されます。
建物譲渡特約付借地権の契約期間は30年以上で、契約終了時に借地上の建物を所有者に譲渡する特約付きの借地権です。建物の買取が確約されるため、土地の返還と同時に建物も所有者の手に渡ることが特徴です。
一時使用目的の借地権
この借地権は法律上、契約期間終了後の更新が認められておらず、短期間の利用に限られています。利用終了後は確実に土地が返還されるため、所有者にとっても安心して貸し出せるという点が特徴です。
借地権の相続税評価額の計算方法
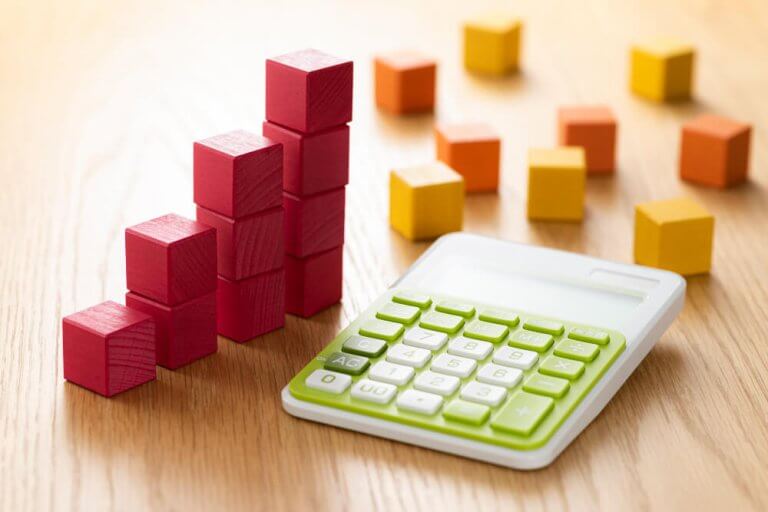
普通借地権の評価方法
計算方法
普通借地権の評価額=自用地価額×借地権割合
定期借地権の評価方法
計算方法
計算方法:定期借地権の評価額=自用地価額×借地権割合×(残存価額率)
一時使用目的の借地権の評価方法
- 雑種地の自用地価額×法定地上権割合と借地権割合の低い方
- 雑種地の自用地価額×法定地上権割合×1/2
借地権の相続税評価額の計算例をケース別に紹介

借りた土地の上に建物を建てている場合
借りた土地の上に自分の建物を建てる普通借地権の場合、評価額は「自用地価額 × 借地権割合」で算出します。この評価額が借地人(借り手)側の相続税評価額となります。
例えば、自用地価額が2,000万円、借地権割合が60%の地域で計算する場合における評価額は
「2,000万円×0.6=1,200万円」です。
他人に土地を貸し、借主が建物を建てている場合
自分の土地を他人に貸し、借主が建物を建てている場合は、貸主側の評価として、「自用地価額 × (1 – 借地権割合)」で評価されます。貸主の立場として、土地の評価額から借地権分を控除した計算です。
例えば、自用地価額が3,000万円、借地権割合が60%の地域で計算する場合の評価額は
「3,000万円×(1−0.6)=3,000万円×0.4=1,200万円」です。
使用貸借により土地を貸し付けている場合
使用貸借により無償で土地を貸している場合においては、相続税法上では借地権として評価されず、貸している土地は自用地としての価額で評価されます。借地権割合は考慮されません。
固定資産税以下の金額で土地を貸している場合
固定資産税評価額以下の安価な地代で土地を貸している場合も、借地権が発生しないため、自用地としての価額で評価します。
相当の地代を受け取っている場合
相当の地代とは、通常の賃料よりも高い水準の賃料でその土地の自用地評価額の年6%程度の金額を支払っているケースです。この場合は、借地権評価額は基本的に自用地評価額の20%で評価します。
例えば、自用地価額が2,200万円の地域で、借地権取引慣行がない場合の評価額は
「2,500万円×(1−0.2)=2,500万円×0.8=2,000万円」です。
借地権取引慣行がない地域の場合
借地権取引の慣行がない地域では、借地権の評価が行われません。この場合も、借地権評価額は基本的に自用地評価額の20%で評価することが可能です。
例えば、自用地価額が2,200万円の地域で、借地権取引慣行がない場合の評価額は
「2,200万円×(1−0.2)=2,200万円×0.8=1,760万円」です。
借地権を相続する際の注意点

- 借地契約の内容確認
- 借地権の評価確認
- 地主の承諾
- 建物の老朽化と承諾
- 地代の変更リスク
まとめ
ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!
お気軽にまずはご相談を!
ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!
どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ
当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。
地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、
ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。
直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。
借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!


