- 借地権HOME
- 借地権の遺産分割協議書の書き方
借地権を相続することになった場合、適切な遺産分割方法を選択し、遺産分割協議書を作成する必要があります。しかし、借地権の遺産分割は一般的な不動産と異なる特徴があり、その手続きや書類作成に不安を感じる方も多いでしょう。
この記事では、借地権の遺産分割方法の種類や特徴、遺産分割協議書の作成方法などを詳しく解説します。現物分割や代償分割、換価分割、共有分割といった各分割方法の特徴を理解し、ご自身の状況に最適な方法を選択することができます。借地権の相続でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事のまとめ】
- 借地権の遺産分割には現物・代償・換価・共有の4方法があります。
複数相続人の場合、トラブル防止のため最適な方法を協議し、選択することが重要です。 - 借地権の分割では代償分割が一般的で承継者が金銭で代償。
換価分割は売却代金分配で公平性が高い一方、共有分割は将来トラブルリスクが高く避けるべきです。 - 遺産分割協議書は相続人全員の合意を明文化する法的文書です。
将来トラブルを防ぐため、記載項目を正確に記入し、相続人全員で作成・保管することが重要です。

監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
借地権の遺産分割方法

借地権を含む遺産の分割方法には、主に4つの方法があります。
相続人が複数いる場合、トラブル防止のために相続人全員で遺産分割協議を行い、以下の分割方法から最適なものを選択する必要があります。
| 分割方法 | 概要 |
|---|---|
| 現物分割 | 土地や建物といった財産を物理的にそのまま分ける方法 |
| 代償分割 | 特定の相続人が遺産を相続し、他の相続人へ代償財産を交付する方法 |
| 換価分割 | 相続対象の財産を売却し、その売却代金を分配する方法 |
| 共有分割 | 複数の相続人で持分を決めて共有する方法 |
現物分割
現物分割とは、借地権を物理的に分割して、各相続人に分配する方法です。相続手続きが比較的簡単で、一般的な遺産分割でよく用いられる方法ですが、借地権の場合は適用が難しいケースが多くなります。
例えば、1つの借地しかない場合は現物分割が困難です。ただし、借地面積が広く、2つ以上に分割できる場合は検討の余地があります。その際は、分割後の各区画で新たに借地契約を結び直す必要があり、それぞれの区画で地代を支払うことになります。
また、分割によって地主の利益が著しく損なわれる場合は、契約解除のリスクも考慮する必要があります。
代償分割
代償分割は、借地権の相続において最も一般的な方法です。特定の相続人が借地権を相続し、その代わりに他の相続人に対して金銭などで代償を支払います。
この方法のメリットは、借地権を分割することなく相続できる点です。また、他の相続人には法定相続分に応じた代償金が支払われるため、相続人の間の公平性も保たれます。例えば、長男・次男の2人が相続人で、2,000万円相当の借地権を長男が相続する場合、長男は次男に1,000万円の代償金を支払うことになります。
ただし、代償金を支払う相続人に十分な資金力が必要となるため、資金面の準備が重要です。代償金の支払いが困難な場合は、他の分割方法を検討しなければなりません。
換価分割
換価分割は、借地権を売却して得た現金を相続人の間で分配する方法です。相続人全員が現金で相続分を受け取るため、分割の公平性が保たれやすいという特徴があります。この方法は、借地権の評価額を具体的な金額として確定できるため、相続人の間の争いを防ぎやすいというメリットがあります。
例えば、3,000万円で借地権を売却できた場合、配偶者が1,500万円、長男・次男がそれぞれ750万円ずつ受け取るといった形で明確に分配できます。
ただし、借地権の売却には地主の承諾が必要で、承諾料の支払いも発生します。また、売却までに時間がかかったり、売却利益に対して課税されたりするデメリットもあります。
共有分割
共有分割は、複数の相続人が借地権を共有する方法です。各相続人の持分を決めて登記し、地代や固定資産税などの費用も持分に応じて分担します。
この方法は、一見すると公平な分割方法に見えますが、実際の運用面では多くの課題があります。例えば、建物の売却や建て替えなどの際には共有者全員の合意が必要となり、意見が分かれた場合の調整が困難になります。また、一部の相続人が地代や税金の支払いを怠った場合のトラブルも懸念されます。
さらに、次世代への相続時には権利関係がより複雑化するリスクもあるため、できるだけ避けることが望ましい分割方法と言えます。
借地権の遺産分割協議書とは
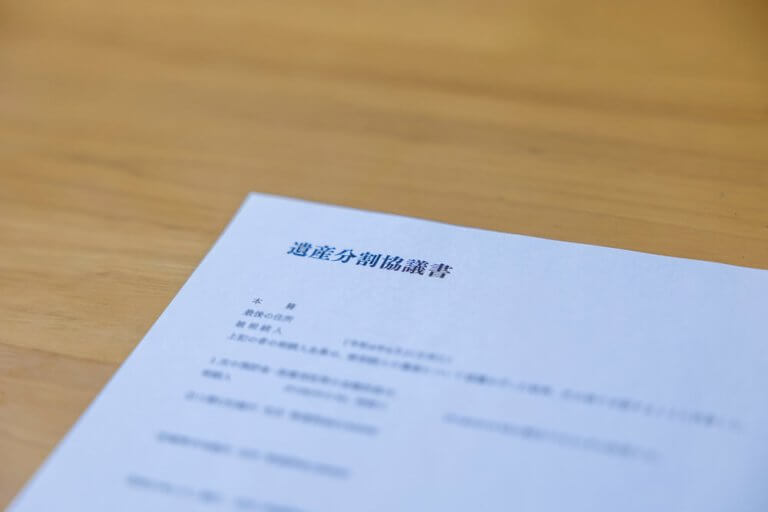
借地権の遺産分割協議書は、相続人全員で借地権の分割方法について話し合い、その合意内容を書面化した法的文書です。これは、相続人の間の権利関係を明確にし、将来的なトラブルを防ぐために非常に重要な書類となります。
特に借地権の場合、土地所有者(地主)との関係性も考慮する必要があるため、分割内容を明確に記録しておくことが重要です。なお、遺産分割協議書の作成には特定の書式は定められていませんが、法的な効力を持たせるためには、必要な項目を漏れなく記載し、相続人全員の合意を得なければなりません。
また、作成した遺産分割協議書は、相続登記の申請時や、金融機関での相続手続きの際にも必要となります。そのため、正確な情報を記載し、相続人全員が保管できるよう、相続人の人数分を作成しましょう。
借地権の遺産分割協議書に記載する項目

借地権の遺産分割協議書に記載する主な項目は以下のとおりです。
- 被相続人の基本情報(氏名、死亡年月日、本籍、登記上の住所など)
- 分割する相続財産の内容
- 相続人全員が分割方法や分割割合に合意している旨
- 相続人全員の住所・氏名・押印(実印)
遺産分割協議書の記載方法には特に定めがないため、任意の書式で作成します。ただし、書面の記載内容が不明確だった場合は提出先から訂正を求められる可能性があります。以降で、借地権の遺産分割協議書の書き方をご紹介します。
借地権の遺産分割協議書の書き方
借地権の遺産分割協議書の文例になります。実際に作成する際に参考にしてください。
遺産分割協議書
被相続人 ●●●●
生年月日 昭和○年○月○日
本籍 東京都◯◯市○○町○丁目○番地
令和○年○月○日、上記被相続人●●●●の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。
1. 次の遺産は▲▲▲▲が相続する。
(1) 下記土地の借地権(賃貸人 ■■■■)
所在 東京都○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○平方メートル
(2) 建物
所在 東京都○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 ○平方メートル /2階 ○平方メートル
2. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、▲▲▲▲が取得することに同意した。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するため相続人ごとに本協議書を作成する。
令和○年○月○日
東京都○○市○○町○丁目
▲▲▲▲(実印)
東京都○○市○○町○丁目
◆◆◆◆(実印)
東京都○○区○○町○丁目
××××(実印)
まとめ
借地権の遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割という4つの方法があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。相続人の状況や借地権の特性を考慮し、最適な分割方法を選択することが重要です。
また、遺産分割協議書の作成においては、必要な項目を漏れなく記載し、相続人全員の合意を得ることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。相続手続きを円滑に進めるためにも、慎重に対応して いきましょう。
借地権無料相談ドットコムでは、借地権に関する相談を無料でお受けしています。借地権の相続、売買、手続き関係など、借地権に関する内容なら幅広く対応しています。さらに、相談から買取までワンストップで可能なため、借地権に関するさまざまな問題はすべて借地権無料相談ドットコムで解決できます。お気軽に、まずはご相談ください。
ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!
お気軽にまずはご相談を!
ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!
どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ
当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。
地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、
ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。
直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。
借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!

