- 借地権HOME
- 借地権の償却について
借地権は事業用資産として重要な役割を持ちますが、その減価償却や会計処理については複雑なルールがあり、多くの事業者が悩みを抱えています。
この記事では、借地権の減価償却の仕組みや、取得・更新・売却といった場面ごとの具体的な会計処理の方法について解説します。借地権を保有する事業者や、今後借地権の取得を検討している方に役立つ情報をご紹介します。
【この記事のまとめ】
- 借地権は、普通・定期ともに原則減価償却の対象外です。
土地の権利で価値が減少しないためです。ただし、普通借地権の更新料は、一定条件で減価償却が認められます。 - 減価償却は、固定資産の取得費用を耐用年数で経費計上する会計処理です。
高額な費用を分散し、企業の財務状態を適切に表示するために重要です。 - 借地権の会計処理は、取得・更新・売却時で異なります。
権利金など資産計上費用と経費を正しく区分し、適切な会計処理が税務問題防止に繋がります。

監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
借地権の種類によって減価償却扱いが変わる
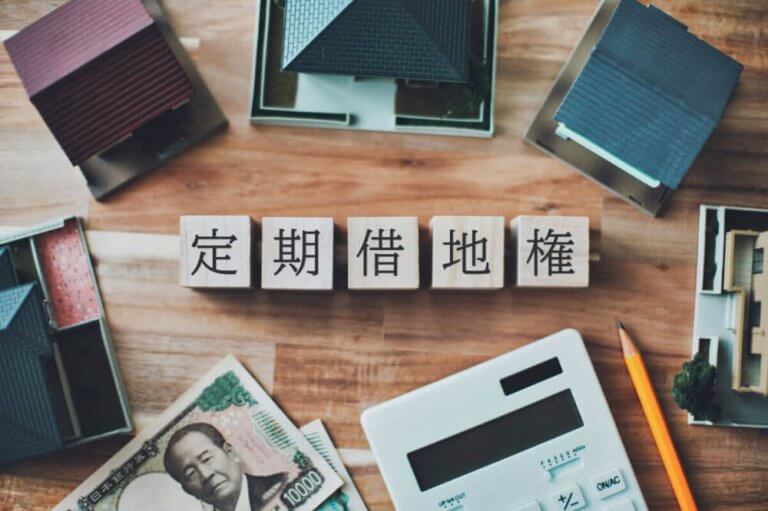
借地権は基本的に非減価償却資産に分類されますが、その種類(普通借地権・定期借地権)と状況によって、一部の費用については減価償却が認められます。特に、更新料の扱いについては借地権の種類によって異なる取り扱いとなっています。
普通借地権は減価償却の対象ではない
- 契約を更新することで半永久的に土地を借りることができるため、時間経過による価値の減少が認められない
- 土地の所有権と同様、時間の経過で価値が減少しない資産として扱われる
- 残存する使用年数を特定できないため、減価償却の計算ができない
定期借地権は減価償却の対象ではない
- 土地に関する権利は、本質的に非減価償却資産として扱われる
- 契約期間が定められているにもかかわらず、税法上は使用によって減価しない資産と考えられている
- 繰延資産としての償却も認められていない
減価償却の仕組み

減価償却とは、事業で使用する固定資産の取得費用を、その資産の使用可能期間にわたって分割し、毎年の経費(減価償却費)として計上する会計処理の方法です。例えば、事務所として使用する建物を4,000万円で購入し、耐用年数が5年となる場合は、年に800万円ずつ発生する減価償却費を5年にわたって計上することになります。
【ケース別】借地権の会計処理の方法

借地権を取得した場合
(貸方)現金 6,000,000
取得に関わる費用(権利金、仲介手数料、改良費など)は、すべて借地権として資産計上します。また、権利金を支払わず「相当の地代」を支払う場合は、以下のように処理します。
(貸方)現金 60,000
借地権を更新した場合
(借方)借地権 30,000
借地権償却費 24,000
(貸方)現金 30,000
借地権 24,000
更新料は「借地権」として資産計上し、同時に借地権の一部が減価したとして「借地権償却費」を計上します。
借地権の認定課税が行われた場合
権利金を支払う慣行がある地域で権利金なしで契約した場合、贈与税または法人税が課される可能性があります。認定課税の金額は、地主と借地権取得者が個人か法人かによって計算方法が異なります。
借地権を売却した場合
(借方)普通預金 XXX
(貸方)借地権 XXX
固定資産売却益 XXX
(借方)普通預金 XXX
(貸方)建物 XXX
借地権 XXX
固定資産売却益 XXX
会計処理が必要な借地権を取得する際にかかる費用

- 権利金:借地権設定の対価として支払う一時金
- 更新料:契約更新時に支払う費用
- 承諾料:地主の承諾を得るために支払う費用
- 仲介手数料:契約締結時の仲介業者への手数料
- 改良費:土地の改良にかかった費用
- 立退料:既存の借地人に支払う立退料
- 建物の取り壊し費用:借地権取得に伴う建物撤去費用
まとめ
借地権は基本的に非減価償却資産として扱われ、普通借地権・定期借地権ともに権利自体の減価償却はできません。ただし、普通借地権の更新料については、一定の条件下で減価償却が認められています。
借地権の会計処理は、取得時、更新時、認定課税時、売却時など、それぞれの場面で適切な処理が求められます。また、取得時には権利金、更新料、承諾料、仲介手数料など、様々な費用が発生しますが、これらは資産計上すべきものと経費処理すべきものを正しく区分する必要があります。
ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!
お気軽にまずはご相談を!
ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!
どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ
当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。
地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、
ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。
直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。
借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!


