- 借地権HOME
- 借地権と抵当権について
【この記事のまとめ】
- 借地権と抵当権の優先順位は、どちらが先に「対抗要件」を備えたかで決まります。
借地上の建物登記が先なら借地権が、土地の抵当権設定が先なら抵当権が優先されます。 - 先に設定された抵当権が優先されると、地主の債務不履行で抵当権が実行されます。
借地人は土地を明け渡し、建物の撤去も求められる可能性があります。 - 借地権そのものには抵当権を設定できませんが、借地上の建物には可能です。
金融機関は地主の承諾を求めることが多く、借地権を担保とする融資は一般的に困難です。

監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
借地権と抵当権のどちらが優先されるかは対抗要件によって異なる

借地権とは
借地権は、建物の所有を目的として土地を借りる権利です。借地人は地主との契約に基づき、地代を支払って土地を使用することができます。借地権には普通借地権と定期借地権があり、いずれも借地借家法によって借地人の権利が保護されています。
抵当権とは
抵当権は、債務者が返済できなくなった場合に、担保物件を競売にかけて債権を回収できる権利です。住宅ローンなどで金融機関が設定することが多く、不動産登記によって対抗要件を備えます。
対抗要件とは
対抗要件とは、当事者間の権利関係を第三者に対して主張するために必要な要件です。借地権の場合は借地上の建物の登記、抵当権の場合は抵当権設定登記が対抗要件となります。
借地権が優先されるケース

借地人が土地に建物を建てて登記を完了した後に、地主が土地に抵当権を設定した場合、借地権が優先されます。抵当権者は借地権付きの土地を担保として取得したとみなされるためです。
抵当権が優先されるケース
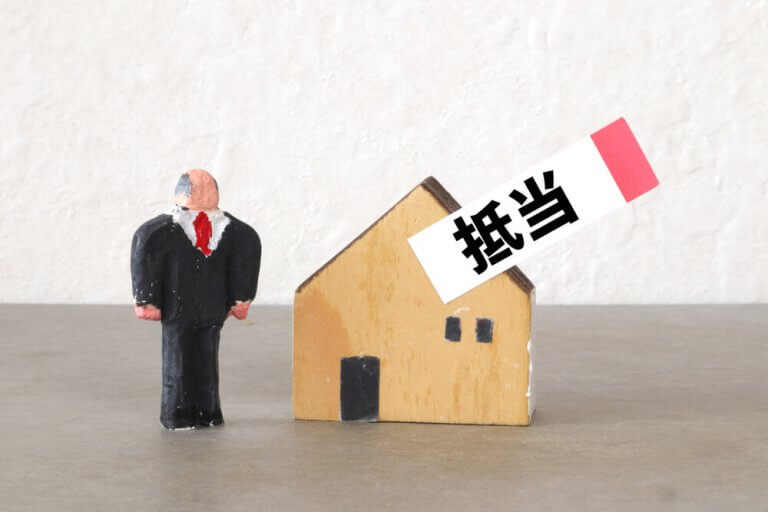
土地にすでに抵当権が設定されている状態で借地権が設定された場合、抵当権が優先されます。抵当権者は更地としての価値を前提に融資を実行しているため、後から設定された借地権による制限を受けないからです。
低地の抵当権が実行された場合、借主は土地を引き渡す必要がある

抵当権の効力が借地権より強い場合、地主が債務を返済できず抵当権が実行されたときには、借地人は建物を収去して土地を更地にして返還しなければなりません。借地契約に違反がなく真面目に地代を支払っていたとしても、地主の債務不履行により立退きを迫られる事態が発生します。
借主は抵当権を設定することができる?

土地を借りている権利そのものには抵当権を設定できませんが、借り主が所有する建物については抵当権の設定が認められています。建物の所有者は借地人であり、自己の所有物である建物に抵当権を設定する権利を持つためです。建物に抵当権を設定した場合、その効力は借地権にも及ぶとされています。
借地権を担保に融資してくれる金融機関はある?
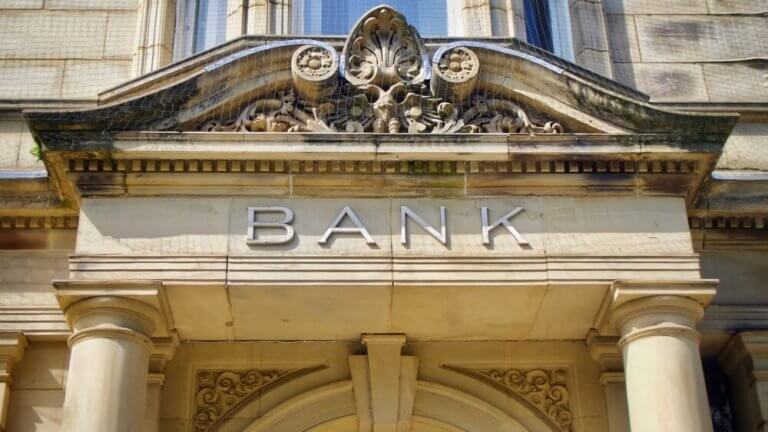
借地権を担保にした融資は、一般の金融機関では審査が厳しく、多くの場合は融資を断られるケースが多くなっています。担保価値の不安定さが主な理由となり、銀行は慎重な姿勢を示します。
ただし、特定の金融機関では借地権を担保とした融資商品を取り扱っています。また、住宅ローンでも、自宅の敷地が借地の場合に対応可能な商品も存在します。融資を検討する場合は、複数の金融機関に相談し、条件を比較検討することが重要です。
まとめ
借地権と抵当権の関係は、登記の前後関係によって優劣が決まります。既に抵当権が設定されている土地で借地権を取得すると、将来的に立退きを迫られるリスクがあるため、事前の確認が重要です。
借地権や抵当権に関する法的問題は、専門的な知識と経験が必要な分野です。借地権無料相談ドットコムでは、借地権に関する相談を無料でお受けしています。借地権の相続、売買、手続き関係など、借地権に関する内容なら幅広く対応しています。さらに、相談から買取までワンストップで可能なため、借地権に関するさまざまな問題はすべて借地権無料相談ドットコムで解決できます。
お気軽に、まずはご相談ください。
関連サイト:
・借地権を担保に融資を受けることは可能?地主からの許可が必要かどうか、抵当権との関係についても解説|HTファイナンス
ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!
お気軽にまずはご相談を!
ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!
どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ
当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。
地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、
ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。
直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。
借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!

