- 借地権HOME
- 借地借家法とは?
土地や建物の賃貸借に関する契約で、「借地借家法」という言葉を耳にしたことはありませんか?
借地権や建物賃貸借契約の更新、解約など、賃貸借に関わる重要な権利や義務を定めているこの法律は、私たちの生活に密接に関係しています。
しかし、「旧法」と「新法」の違いや、借地権の種類、契約の更新条件など、理解すべき内容は多岐にわたり、土地を借りる側も貸す側も戸惑うことが少なくありません。
この記事では、借地借家法の基本から具体的な適用事例まで、実務的な観点からわかりやすく解説します。この記事を読めば、賃貸借契約に関する基礎知識が身につき、安心して契約を結ぶことができるようになります。
【この記事のまとめ】
- 借地借家法は賃借人を保護する特別法です。
賃借人に不利な契約条項は無効となる強行規定であり、正当な事由がなければ賃貸借契約の更新を拒否できないなど、借りる側の権利を手厚く保護しています。 - 旧法による土地活用停滞を受け新法が制定されました。
旧法は借地人を強く保護し土地活用が進まなかったため、1992年に新法が制定。定期借地権を創設し土地の有効活用を促進しました。 - 借地権は「普通」と「定期」に大別されます。
新可能な普通借地権と、期間満了で更新されない定期借地権に分かれ、さらに定期借地権は、利用目的や終了時の扱いによりさらに3種類に細分されます。

監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
借地借家法とは?
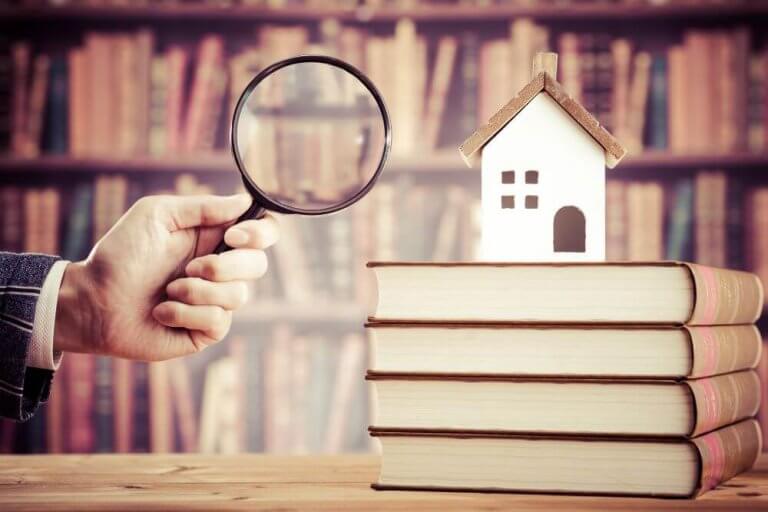
借地借家法は、建物の所有を目的とした土地の賃借権(借地権)と建物の賃貸借契約に関する特別法です。
土地や建物を借りる人(賃借人)と貸す人(賃貸人)との間の権利や義務を定めており、特に賃借人の権利を保護する目的で制定されています。この法律の大きな特徴は、以下の3点です。
借地に関するルール
- 土地を借りて建物を所有する場合の権利(借地権)について定めています
- 借地権の存続期間は最低30年
例:マイホームを建てるために土地を借りている場合、30年間は安心して住み続けることができます
借家に関するルール
- 建物を借りる場合の賃貸借契約について定めています
- 正当な事由がない限り契約更新を拒否できません
例:賃貸マンションに住む人が家賃を適切に支払っている限り、大家さんは正当な理由なく退去を求めることはできません
強行規定としての性質
- 借地借家法の規定に反する契約条項で借地人や借家人に不利なものは無効
例:契約書に「更新は一切認めない」と書かれていても、法律上の要件を満たせば更新できます
【ここがポイント!】
- 借地権・借家権とも、正当な事由がない限り更新拒否できません
- 契約書の内容より借地借家法が優先されます
- 賃借人(借りる側)の権利が手厚く保護されています
このように、借地借家法は私たちの住生活を守る重要な法律です。
土地を借りて家を建てる場合も、アパートやマンションを借りる場合も、この法律によって安定した居住が保障されています。
借地借家法の歴史

借地借家法は、長年の法改正を経て現在の形になりました。
その始まりは1909年の建物保護に関する法律の制定です。この法律により、建物の登記があれば借地権を第三者に主張できるようになり、借地権保護の第一歩となりました。
その後、1921年に借地法と借家法が制定され、建物所有を目的とした土地利用や借家人の権利が具体的に保護されるようになります。特に昭和時代に入ると、戦時下における借地人の生活安定を重視し、1941年の法改正で地主による更新拒否が制限されました。さらに1966年には、借地権の譲渡や転貸に関する規定も整備され、借地人の権利は一層強化されました。
現在の借地借家法は1992年に施行され、それまでの法律を一本化するとともに、新たに定期借地権制度を創設しました。この改正では借地権の存続期間を30年以上に統一し、土地の有効活用も考慮した制度設計がなされています。なお、この法改正以前に締結された契約には旧法が適用され続けるため、現在も新旧の法律が併存している状況です。
このように、借地借家法は時代とともに変化する社会のニーズに応じて発展してきた法律といえます。
新法借地権とは?設定された背景・目的

平成4年8月に施行された新法借地権は、それまでの旧借地法を大きく見直し、現代社会のニーズに対応した新しい借地制度として誕生しました。
旧借地法では「一度土地を貸したら永久に返ってこない」と言われるほど、借地人の権利が強く保護されていました。たとえば、地主は正当な事由がない限り契約更新を拒否できず、更新期間も建物の種類によって30年や60年と長期に設定されていました。そのため、地主は土地を貸すことに消極的になり、結果として土地の有効活用が進まないという社会問題が生じていました。
この課題を解決するため、新法借地権では以下の改革が行われました。まず、建物の種類による区別をなくし、借地権の存続期間を一律30年以上としました。更新についても、最初の更新は20年、2回目以降は10年と、より現実的な期間設定になりました。
さらに、画期的な制度として「定期借地権」が新設されました。これは契約期間満了後に確実に土地が返還される仕組みで、50年以上という長期の利用を前提としながらも、将来の土地活用の計画を立てやすい制度となっています。
このように新法借地権は、借地人の権利を守りながらも、土地所有者が安心して土地を貸せる環境を整備し、土地の有効活用を促進することを目的として設定されました。
旧法と新法に関する注意点

借地権の更新の際に良くある質問ですが、一度旧法で取り交わした契約については更新後でも新法は適用されず、引き続き旧法が適用されます。
この点では更新時などには注意が必要でしょう。
新法の特徴としても、契約期限が過ぎたときに貸し手に土地が確実に戻るように貸借期間を一定期間に限った「定期借地権」を設定したことにもその背景が現れています。
新法借地権と旧法借地権の違い

新法借地権と旧法借地権では、主に存続期間と建物の区分、契約更新の仕組みに大きな違いがあります。
旧法借地権では、建物を「堅固な建物」と「非堅固な建物」に区分し、それぞれで存続期間が異なっていました。堅固な建物(鉄骨鉄筋コンクリート造など)の場合は存続期間が30年で更新後も30年、非堅固な建物(木造建築など)の場合は存続期間が20年で更新後も20年と定められていました。
一方、新法借地権では建物の構造による区分をなくし、存続期間を一律30年以上としました。更新期間については、最初の更新時は20年、2回目以降は10年と定められ、より現実的な期間設定となっています。
また、新法では「定期借地権」という新しい制度が創設され、契約期間満了で確実に終了する借地権が設定できるようになりました。これは旧法にはない制度で、50年以上という長期の利用を前提としながら、期間満了時には更新なく土地を返還する仕組みです。
さらに、建物の老朽化による借地権の消滅についても違いがあります。旧法では期間の定めのない契約の場合、建物が朽廃すれば借地権が消滅しましたが、新法ではそのような規定はありません。
なお、平成4年8月の新法施行以前に設定された借地権には、原則として旧法が適用され続けるため、現在も新旧両方の借地権が併存している状況です。
旧法借地権から新法借地権へ切り替えはできる?
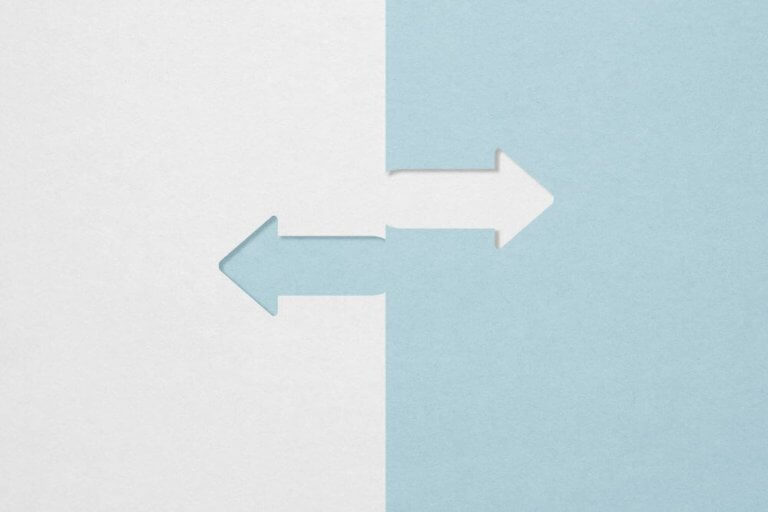
旧法借地権から新法借地権への切り替えは、原則としてできません。これは借地借家法の附則(付則)で、「この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法により生じた効力を妨げない」と定められているためです。
つまり、平成4年8月の新法施行以前に設定された借地権は、賃借人(借地人)の既得権として保護されているのです。これは、借地人の権利を手厚く保護していた旧法下で契約を結んだ借地人の利益を守るための規定といえます。
ただし、当事者間(地主と借地人)の合意があれば、新法借地権への切り替えは可能です。例えば、契約更新時に双方の話し合いにより、新法の適用を受ける契約に変更することができます。しかし、これは借地人の権利を一部放棄することになるため、実務上はあまり例がありません。
このように、新旧の借地権は並存し続けることが前提となっており、既存の権利関係を尊重する形で新法が運用されています。
借地借家法で定められている借地権の種類

借地権は、大きく「普通借地権」と「定期借地権」の2つに分類されます。これらは契約の更新の可否や存続期間、利用目的などで異なる特徴を持っています。
- 普通借地権
- 定期借地権
以下、それぞれの特徴と違いについて詳しく解説していきます。
普通借地権
普通借地権は、最も一般的な借地権の形態で、契約期間が30年以上と定められ、更新が可能な借地権です。借地契約を更新する場合、1回目の更新では20年以上、2回目以降は10年以上の期間で設定されます。
普通借地権の最大の特徴は、土地上に建物が存在する限り、地主に正当な事由がない限り更新を拒否できないことです。また、契約が終了する場合でも、借地人には建物の買取請求権が認められています。
このように、普通借地権は借地人の権利を手厚く保護する制度となっています。
定期借地権
定期借地権は、平成4年の借地借家法制定時に新設された制度で、契約期間満了により確定的に契約が終了する借地権です。普通借地権とは異なり、原則として契約の更新はできず、期間満了時には建物を取り壊して更地にして返還する必要があります。
定期借地権は、その利用目的や契約内容によって「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3種類に分かれています。それぞれ存続期間や利用目的、契約終了時の取り扱いなどが異なりますので、以下で詳しく説明していきます。
一般定期借地権
一般定期借地権は、存続期間を50年以上と定め、契約期間満了後は更新がなく、建物を取り壊して更地で返還する借地権です。住居用・事業用を問わず利用できる点が特徴で、契約締結時には公正証書等の書面により、更新がないこと、建物の再築による期間延長がないこと、借地人による建物買取請求権を行使しないことを定める必要があります。
この制度は、定期借地権付きマンションなどで広く活用されており、50年以上という長期の利用を前提としながらも、土地所有者にとって将来の土地活用が確実に計画できるメリットがあります。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上と定め、期間満了時に借地人が所有する建物を地主が買い取ることを約束する借地権です。一般定期借地権とは異なり、建物の取壊しは不要で、居住用・事業用を問わず利用できます。
特徴的なのは、契約終了後も建物の賃借人として居住し続けることができる点です。建物を地主に譲渡した後、賃借人として引き続き建物を使用したい場合は、期間の定めのない賃貸借契約が成立したものとみなされます。
事業用定期借地権
事業用定期借地権は、店舗やオフィスなど事業用の建物に限定して利用できる借地権です。存続期間は10年以上50年未満で設定され、居住用途での使用は一切認められません。契約は必ず公正証書で行う必要があり、期間満了時には建物を取り壊して更地で返還します。
この制度は、比較的短期間での事業用地の有効活用を目的としており、コンビニエンスストアやファミリーレストランなどの出店に多く利用されています。地主にとっては、事業用に限定することで将来の土地利用の選択肢を確保しやすいというメリットがあります。
借地借家法で定められている借地権は更新できる?

借地権の更新の可否は、借地権の種類によって異なります。以下の表で借地権の更新について整理してみましょう。
| 更新できるもの | 特記事項 |
|---|---|
| 旧法借地権 | 建物の種類により更新期間が異なる(堅固建物:30年、非堅固建物:20年) |
| 普通借地権 | 1回目の更新:20年以上、2回目以降:10年以上 |
| 更新できないもの | 特記事項 |
|---|---|
| 一般定期借地権 | 存続期間 50年以上で確定 |
| 事業用定期借地権 | 存続期間 10年以上50年未満で確定 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 期間満了時に建物を地主が買取り |
まとめ
借地借家法は、土地や建物の賃貸借において重要な役割を果たす法律です。特に平成4年の新法施行により、普通借地権に加えて定期借地権が新設され、より柔軟な土地活用が可能となりました。
建物所有者の居住権を守りながら、土地所有者の将来的な活用も考慮された制度設計となっています。借地借家法の内容を理解することで、契約当事者の権利と義務を把握し、トラブルのない賃貸借関係を築くことができます。また、定期借地権など新しい制度を活用することで、それぞれのニーズに合った土地活用の選択肢が広がります。
借地権無料相談ドットコムでは、借地権に関する相談を無料でお受けしています。借地権の相続、売買、手続き関係など、借地権に関する内容なら幅広く対応しています。さらに、相談から買取までワンストップで可能なため、借地権に関するさまざまな問題はすべて借地権無料相談ドットコムで解決できます。
お気軽に、まずはご相談ください。
ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!
お気軽にまずはご相談を!
ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!
どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ
当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。
地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、
ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。
直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。
借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!



