- 借地権HOME
- 土地は借地で家は持ち家とは?
【この記事のまとめ】
- 「土地は借地で家は持ち家」とは、建物を自己所有し、土地は地主から借りている状態です。
建物には固定資産税、土地には地代がかかります。相続も可能ですが、借地権の種類確認が重要です。 - 「土地は借地で家は持ち家」を相続する際は、登記簿や契約期間、地代の確認が必須です。
遺産分割協議後、地主へ連絡し、建物の相続登記と名義変更、相続税の支払いを行います。 - 相続後は、建物の固定資産税負担や、増改築・売却時の地主許可、契約満了時の更地返還義務に注意が必要です。
地主とのトラブルを防ぐため、良好な関係維持が重要です。

監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
土地は借地で家は持ち家とは

持ち家の借地権とは
借地権とは、他人の土地に建物を所有するための権利のことで、主に「地上権」と「賃借権」の2種類があります。地上権は物権として強い権利を持ち、土地登記簿に必ず記載され、抵当権の設定も可能です。一方、賃借権は債権として位置づけられ、登記は不要で、抵当権の設定はできません。
「土地は借地で家は持ち家」は相続できる
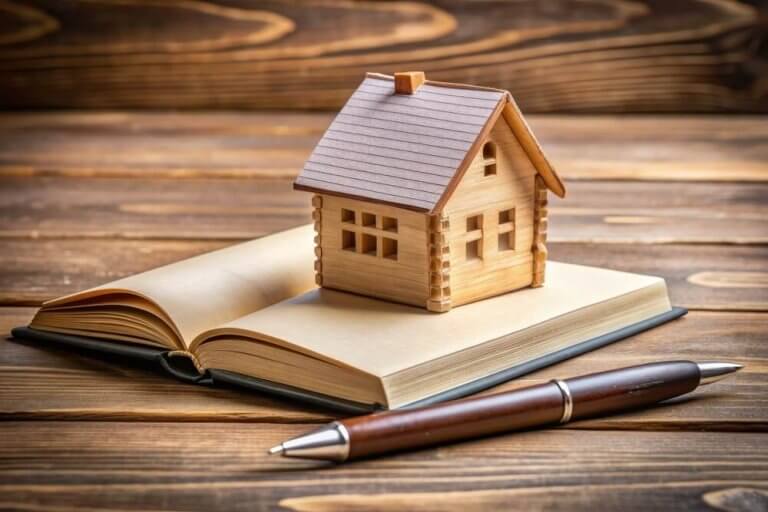
土地は借地で家が持ち家の物件は相続することが可能です。相続する際には、登記簿謄本や契約書の確認、地代の支払い状況など、いくつかの重要な事項を確認する必要があります。
また、相続の際は地主の承諾は法的には不要ですが、良好な関係を維持するためにも丁寧な対応が求められます。
登記簿謄本を確認する
相続時にまず行うべきことは、最寄りの法務局で登記簿謄本を確認することです。これは、建物の所有権や土地の権利関係を正確に把握するためです。借地権は通常、賃借権として設定されており、多くの場合は登記されていませんが、相続する際には相続登記が必要です。
契約期間を確認する
相続時には、借地権の契約期間を必ず確認しましょう。契約書で定められた期間や更新のタイミングを把握することは、今後の土地利用の計画を立てる上で極めて重要です。1992年8月以前の契約の場合は契約書が存在しないこともありますが、その場合は地主と連絡を取り、契約内容を明確にしておく必要があります。
地代を確認する
地代の確認も相続時の大切なチェックポイントです。借地権を維持するためには地代の支払いが必要なため、その金額や支払い方法を正確に把握しておきましょう。地代の相場は、一般的に路線価や固定資産税などを基準に設定されており、長年変更されていない場合は、相続を機に見直しを求められることもあります。
「土地は借地で家は持ち家」を相続する際の流れ
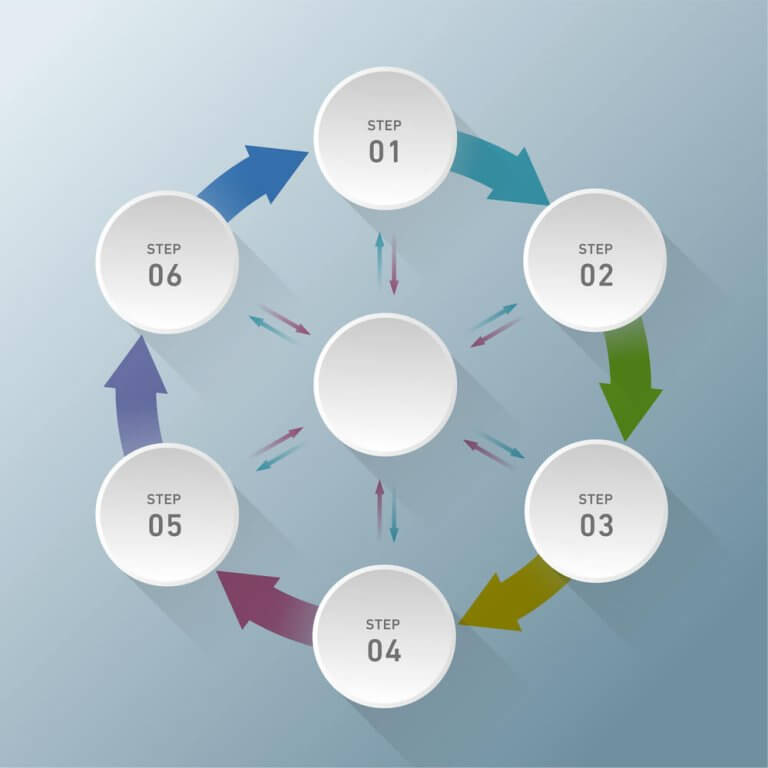
- 借地権の確認をする
- 遺産分割協議を行う
- 地主へ連絡する
- 建物の相続登記を行う
- 持ち家の名義変更を行う
- 相続税を支払う
1. 借地権の確認をする
借地権の相続手続きの第一歩は、借地権の内容を詳細に確認することです。具体的には、賃借権か地上権か、定期借地権か普通借地権かといった権利の種類を把握します。また、現在の地代はいくらか、更新料についての取り決めはあるか、地主との特別な約束事項はないかなども確かめてください。
2. 遺産分割協議を行う
共有名義での相続は将来的なトラブルの原因となりやすいため、できるだけ避けることが望ましいでしょう。
3. 地主へ連絡する
借地権の相続自体には地主の承諾は必要ありませんが、良好な関係を維持するためにも、丁寧な説明と情報共有を心がけましょう。地代の支払い方法や、今後の契約更新についても確認しておくとよいでしょう。
4. 建物の相続登記を行う
借地上の建物については、今後の方針(継続使用、売却、取り壊しなど)に関わらず、まず相続登記を行う必要があります。これは、所有権移転の登記を行うために必要な手続きです。ただし、建物を取り壊す場合、事前の相続登記は不要です。
5.持ち家の名義変更を行う
持ち家の名義変更は、将来的なトラブルを防ぐために重要な手続きです。必要な書類は、遺産分割協議書または遺言書、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで確認できるもの)、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、相続人の住民票、固定資産税評価証明書などがあります。
6.相続税を支払う
借地権も相続税の課税対象となります。相続税の評価額は「土地の価格×借地権割合」で計算します。土地の価格は路線価や倍率方式で算出し、借地権割合は国税庁が地域ごとに定めている割合を使用します。これらの割合は国税庁ホームページの「路線価図・評価倍率表」で確認できます。
参考:財産評価基準書路線価図・評価倍率表|国税庁「土地は借地で家は持ち家」を相続する際の注意点

- 地主とのトラブルに注意
- 建物の固定資産税は、相続人が負担する必要がある
- 増改築や売却をする際には地主の許可が必要
- 契約期間が満了し更新もしなかった場合は、更地返還が原則
地主とのトラブルに注意
これらのトラブルを防ぐためには、相続が発生した時点で速やかに地主に報告し、今後の方針について丁寧に説明することが重要です。また、地代の支払いを滞らせないことも、良好な関係を維持する上で欠かせません。トラブルが発生した場合は、借地権に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
建物の固定資産税は、相続人が負担する必要がある
借地権の場合、土地の固定資産税は地主が負担しますが、建物の固定資産税については相続人が支払う必要があります。固定資産税の納税義務者は1月1日時点の登記上の所有者ですが、相続が発生すると、その納税義務は相続人に承継されます。名義変更の手続き前でも、固定資産税の納付義務は発生しているため注意しましょう。
増改築や売却をする際には地主の許可が必要
相続した建物を増改築したり、第三者に売却したりする場合は、必ず地主の許可を得てください。これは、借地権が土地の利用権であり、その利用方法や権利の譲渡に制限があるためです。許可を得る際には承諾料の支払いを求められることもあります。
契約期間が満了し更新もしなかった場合は、更地返還が原則
借地契約の期間が満了し、更新を行わなかった場合は、建物を取り壊して更地の状態で土地を返還するのが原則です。この際の建物の解体費用は、原則として借地人(相続人)が負担することになります。
まとめ
借地権無料相談ドットコムでは、借地権に関する相談を無料でお受けしています。借地権の相続、売買、手続き関係など、借地権に関する内容なら幅広く対応しています。さらに、相談から買取までワンストップで可能なため、借地権に関するさまざまな問題はすべて借地権無料相談ドットコムで解決できます。
お気軽に、まずはご相談ください。
参考情報:
ぴったりの町が見つかる2拠点・移住ライフ大学
2拠点・移住ライフ大学は、地方創生・関係人口の創出、移住や2拠点生活をしたい人に向けたポータルサイトです。
参考情報:
海外不動産投資ポータルサイト「WorldInvest」は、日本人投資家のための海外不動産投資情報を提供する会社です。
ドバイ不動産、フィリピン不動産、カンボジア不動産、エジプト不動産・・・と幅広い外国の不動産投資情報を提供します。
参考情報:
MoneQ | 無料で楽しくお金の知識(金融リテラシー)を学べるアプリ
MoneQ(マネク)は、無料で楽しくお金の知識(金融リテラシー)を学べるアプリです。
お金のクイズをメインとして、学習プログラムで、スキマ時間に簡単にお金の知識(金融リテラシー)を高めることができます。
ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!
お気軽にまずはご相談を!
ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!
どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ
当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。
地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、
ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。
直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。
借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!



